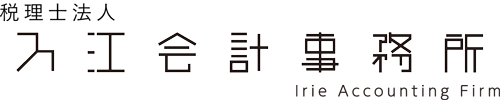創業計画書「9自由記述欄」欄に書くべき項目と審査評価を上げる資料の作り方とは?

創業計画書「自由記述」欄は、追加でアピールしたいことや欲しいアドバイスなどを記入する箇所とされていますが、意外と何も記入しないという方が少なくありません。
しかし、集客の根拠となる資料をつけたり、記入することで、さらなる評価アップを狙うことができます。
この記事では、創業計画書「自由記述」欄に書くべき項目と審査評価を上げる資料の作り方について解説いたします。
「自由記述」欄に書くべき項目は何がよい?
満額融資の獲得に重要なのは、いかにその計画の根拠を明確に金融機関の担当者に伝えられるかということです。
そして、その際にもっとも重要となるのが「”売上げ”の根拠」です。
自己資金や経費については通帳や見積書を提示すればある程度その内容を説明できますが、売上げについては「なぜ、その金額の売上げが立てられるのか?」や「予想通りの集客ができるのか?」を納得してもらうのが困難です。
そのため、売上げの根拠を示すものとして、おすすめなのが次の資料です。
- 商圏内での人口や競合の調査
- 事業のスケジュール
- 売上げを作るための仕組み
- 見込み客の存在を示す資料
これらはいずれも確実な売上げを示すものではありませんが、売上げを上げる根拠となり得るため、融資審査でも評価の向上につながります。
すべての資料をつける必要はありませんが、これから行う事業の内容に応じて「とくにここを説明したい」というときに提出するとより効果的となります。
商圏内での人口や競合の調査
人口等の調査について
誰が見ても納得のいく事業計画を作るためには、その計画が信用のおけるデータにもとづいて作られたものかどうかということが重要となります。
創業計画を作るときには、出店予定地の人口や環境の状況がどうなっているかが重要な要素となりますが、その調査の際に役立つのが政府による基本的なデータです。
たとえば、総務省の「住民基本台帳人口・世帯数動態(市区町村別)」を利用すれば、市町村単位での男女別人口や世帯数の増減率などがわかるため、商圏における基本的な調査に役立ちます。
参考:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
また、独立行政法人統計センターの「地図で見る統計(jSTAT MAP)」を使えば、自分の指定した地域の商圏に関する人口データを取得することができます。
さらに、店舗の近辺に駅や公共施設等がある場合には、その利用者数を調べることで、潜在的な顧客数を確認することができます。
以下のサイトでは、路線ごとの駅の乗降客数や空港利用者の数を視覚的に調べることができるため使いやすいといえます。
参考:駅乗降客数ランキング https://opendata-web.site/station/
| 商圏調査報告 | 令和〇年〇月〇日 | ||||||
| 駅名 | 恵比寿駅 | 中目黒駅 | 五反田駅 | ||||
| 乗降客数 | JR山手線 | 218,898人 | 東急東横線 | 198,683人 | JR山手線 | 270,979人 | |
| JR埼京線 | 64,835人 | 日比谷線 | 168,131人 | 東急池上線 | 101,318人 | ||
| 日比谷線 | 107,471人 | 都営浅草線 | 61,607人 | ||||
| 500m圏内 | 人口総数 | 12,693人 | 13,869人 | 10,187人 | |||
| 昼間人口 | 43,799人 | 21,876人 | 49,783人 | ||||
| 世帯数 | 7,245世帯 | 7,613世帯 | 5,933世帯 | ||||
| 20代男性 | 947人 | 1,181人 | 896人 | ||||
| 30代男性 | 1,332人 | 1,381人 | 1,023人 | ||||
| 40代男性 | 828人 | 949人 | 662人 | ||||
| 50代男性 | 799人 | 840人 | 677人 | ||||
| 全事業所数 | 2,924所 | 1,377所 | 2,333所 | ||||
| 小売事業所数 | 447所 | 277所 | 272所 | ||||
踏査調査について
統計データだけではわからない出店地の状況や競合店の存在、人の流れなどを知るためには、実際に現地に赴き調査をすることが不可欠です。また、現地を踏査することで、それまで気づかなかったデメリットや改良点を見つけることができます。
たとえば、出店地の付近を地図で確認しながら歩いてみることにより、次のような情報を知ることができます。
- 出店候補地の周囲には2校の専門学校と予備校が存在しており、昼間から夕方にかけて100人/hほどの往来があり、一部の学生の通学路ともなっている。
- 商店街の中心部にあるス-パーが商店街全体の集客に大きく貢献しており、また、食品コーナーについては深夜営業(~12:00)を行なっていることから通勤客の流れが終電まで続いている。
- 付近にはJRと営団線の駅が一つずつあり、アクセスは良好である。
- 出店予定地のある商店街への車での侵入は規制されているため、主なターゲットは周周の徒歩、自転車客に限られる。
- 半径500m圏内における競合店は3件だけだが、一部のコンビニでパンの販売に力を入れており、また、イートインスペースもあることから競合になる可能性が高い。
競合店の調査の例
| A店 | B店 | C店 | |
| 予測利用者数 | 100〜150人/日 | 80〜100人/日 | 50〜80人/日 |
| 予測購買額/人 | 600〜700円 | 500〜600円 | 400〜500円 |
| 特徴 | 広い・きれい | 中規模、活気あり | 狭い、暗い感じ |
| パンの種類 | 20〜25種類 手作り | 15〜20種類 手作り+既製品 | 15〜20種類 既製品がメイン |
また、実際に競合店を利用してみることで、外観からではわからない特徴や雰囲気を知ることができるため、できるだけ実際に競合店を利用してみることをおすすめします。
事業のスケジュール
本来、計画には事業のスケジュールが欠かせませんが、これを作らずに計画をすすめてしまう方が少なくありません。
事業のオープンまでにすべきことには、会社の設立手続き(法人化する場合)から賃貸契約の締結、内外装工事の発注、融資の申込みなどがありますが、スケジュールを立てなければ、何をどの順番で進めるべきかや、工程に問題がないかということを確認できません。
日本政策金融公庫の創業計画のフォーマットでは、創業の動機や購入予定の物品や経費などは記入しますが、それだけでは全体的な手続きの流れや進行がわからないため、これを補うためにスケジュール表を作る必要があります。
スケジュール表を作るメリットには、次のようなものがあります。
自分自身が計画を実行するうえでの目安とすることができる。
各工程を確認することで、作業に必要な期間の確保や、作業の漏れ、重複を防ぐことができる。
とくに、融資の申込みをする場合に注意しなければならないのが「許認可の取得」です。
たとえば、飲食店の開業のためには、保健所の営業許可が必要となりますが、営業許可の検査は店舗の工事がある程度済んでいないとすることができません。
なぜなら、許可の検査時には、内装ができていることや、衛生設備の設置、電気・水道が使えるようになっていることなどが必要だからです。
そのため、工事の予定や実際の進捗状況を予想しながら、保健所と検査日程をスケジューリングをしたり、工事業者との打ち合わせをする必要があります。
さらに融資が出るまでには、申し込みから約1ヶ月程度の時間がかかりますが、これらの手続きはこの期間内にしなければならないため、綿密なスケジュールを計画しなくてはなりません。
このように開業準備は、各工程を一斉に始められるわけではなく、取りかかる順番と期限が決められているため、それに合うようにスケジュールを組むことが重要となります。
| 項 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
中 略 | 備 考 |
| 【登記手続関連】 定款認証 資本金払い込み 登記申請~完了 | ||||||||||
| 資本金3,000 | ||||||||||
| 【賃貸契約関連】 手付金支払い 契約締結 保証金等支払 | ||||||||||
| 〇 | 手付100 | |||||||||
| 〇 | 契100 礼100 | |||||||||
| 保600 | ||||||||||
| 【工事関連】 業者選定 着手金支払い 工事着手~完了 引渡し、清算 | ||||||||||
| 〇 | 着手1,500 | |||||||||
| 精算1,500 | ||||||||||
| 【営業許可関連】 事前確認 許可申請 ・実地検査 ・許可証交付 | ||||||||||
| 申請から3~5日 | ||||||||||
| 検査から5~7日 | ||||||||||
| 【融資関連】 資料作成 融資申し込み 面 談 | ||||||||||
| 【その他】 求人、面談 トレーニング 備品購入、仕入れ 開店準備 | ||||||||||
| open |
なお、上記のスケジュール表の項目や工程はあくまで見本ですので、自分でスケジュールを立てるときには適宜、内容を実態に修正した上でご利用してください。
売上げを立てるための仕組みについて
事業を実際に実現可能性なものとするためには、「売上げを立てるための仕組み」が必要となります。
この仕組みがあってはじめてモノやサービスが売れるため、これを無視した事業計画は「絵にかいた餅」となってしまいます。
よくある事業計画書で何の根拠もなく、対前年○%UPの売上げ見込みを立てているものや、単に年間目標額を12で割っただけというものを見かけますが、それでは何の根拠も戦略もない行き当たりばったりのものとなってしまいます。
そのため、金融機関の担当者に計画の内容を信じてもらうためには、計画の売上げを実現化させる仕組みが欠かせないものとなります。
売上げの仕組みというと難しく聞こえますが、要は事前に調査をしたデータを活かして、どのような手順や方法で集客をするのかを形にしたものとなります。
たとえば、通常の集客を行う際には、次のような手順が必要となります。
① 明確な事業のコンセプトの決定
② 具体化な集客方法の決定(どんな方法で集客するか?)
③ 個別の集客対策をどのように展開して成果につなげていくのか?
これらの手順を示したものが、「集客の仕組み」となります。
なお、「仕組み」とは、チラシの配布やホームページの作成といった個々の対策ではなくは、これらを活用して結果を出すための一連の施策として行うものであるということに注意が必要です。
集客の仕組みの例としては、次のようなものが考えられます。
<集客の仕組みの例>
(オープン時)
・ 開業前に営業エリア内でのチラシを10,000枚配布(手渡しまたは投げ込み)
・ 専用アカウントでのツイッターの告知およびフォロワー1,000人の獲得
・ オーブニングイベントとして、全品50%での販売(2日間) 目標:250人×2日
(オープン後)
・ 時点で作成しているパンのレシピを順次公開
・ 近隣の主婦を対象としたパン教室の開催 目標5人×月3回
・ オリジナルパンの募集コンクール
・ 店内の一部スペースを利用したイートインカフェの併設 壁側4人席
オープニング集客見込み
・チラシより 500人
・SNSより 20人
・タウン誌より 50人 ※一週間掲載
・口コミ、紹介 30人
計 600人 ※一日当たり300人
売上げ目標 700円/人×300人×50% = 105,000円/日
見込み客の存在を示す資料
創業時に一定数の見込み客がいるかどうかは、その後の経営の速度を左右するだけでなく、売上げを裏付ける根拠となるため非常に重要といえます。
そのため、ある程度の見込み客がいることを金融機関の担当者に信じてもらえれば、審査の上でも大きなアドバンテージとなります。
しかし、「開業したばかりでそんな見込み客はいない」とお考えの方は多いと思いますが、誰もが簡単に見込み客を作ることが可能です。
その方法は「過去にもらった名刺を使って、見込み客の根拠にする」というものです。
ある程度の開業準備をしている方であれば、事前に交流会や名刺交換会に参加していると思います。また、そのような会へ参加していなくても、それまでの仕事の関係で交換した名刺の数は相当数に上るはずです。
この名刺をA3用紙などですべてコピーしたものを提示すれば、それが十分な見込み客の資料となります。
金融機関では、このような「目に見える形の資料」を重視します。
なぜなら、創業計画の内容はすべて文章や数字ばかりのため、なかなかその実態があるのかどうかを判断しにくいからです。
しかし、このような見える形の資料があれば、計画の内容についても信ぴょう性が高いと判断してもらいやすくなります。
したがって、見込み客がいないという場合には、ぜひおすすめしたい方法です。
まとめ
創業計画書「自由記述」欄については、根拠についての資料を追加したり、記入することで、創業計画書の本文では伝えられなかった強みをアピールすることができます。
とくに、項目に入っていない、競合調査の結果やスケジュールなどは、計画の根拠や実現可能性を裏付ける重要な資料となるため、積極的に作成することをおすすめします。
また、これらの説明に際しては、文字だけでなく、表や図などをつけるとさらにわかりやすくなり、高い評価を得やすくなります。

「いい税理士さんに出会えてよかった」と言われるために、従業員一同情熱と信念を持って業務に取り組んでおります。税金についてだけではなく「補助金」「融資」「経営」などについて不安なこと、わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。