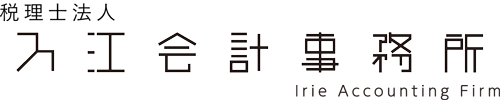創業計画書「8事業の見通し」の書き方のコツと融資確率を高める事例を紹介!

日本政策金融公庫の創業計画「事業の見通し」の箇所は、計画全体の結果となる部分であり、この内容が融資審査に大きな影響を与えることとなります。
そのため、ここではいかに計画の内容が妥当であり、実現の可能性が高いかをわかりやすく表現する必要があります。
この記事では、創業計画書の「事業の見通し」の箇所の正しい記入の仕方と、審査の評価を上げるテクニックを詳細に説明します。
「事業の見通し欄」の概要とポイント
創業計画書の「事業の見通し」欄は、通常の財務諸表でいうところの損益計算書にあたる部分です。
ここには、売上げの見込みと事業に関する経費や利益を記入しますが、以下のポイントを押さえて作成すると計画がまとめやすくなります。
売上高について
売上げを記入するときには
・業種にあった売上げの見込みを立てる
・納得のできる根拠にもとづいて見込みを立てる
の2つに注意する必要があります。
業種にあった売上げの見込みを立てる
売上げの見込みの立て方は、業種により異なります。
そのため、業種に合わない方法で見込みを立ててしまうと、大きな間違いやつじつまの合わない結果の原因となります。
代表的な業種における売上げ見込みの立て方には、次のようなものがあります。
① 販売業で店舗売りのウェイトが大きい業種
<算式> 1㎡(または1坪)当たりの売上高 ×売場面積
[設例] 業種:コンビニエンスストア
・ 売場面積 100㎡ ・ 1㎡当たりの売上高(月間) 14万円
※「小企業の経営指標」による業界平均から算出)
売上予測(1ヵ月)=14万円×100㎡=1,400万円
② 飲食店営業、理・美容業などサービス業関係業種
<算式> 客単価 × 設備単位数(席数) × 回転数
[設例] 業種:美容店
・ 椅子 2台
・ 1日1台あたりの回転数 4.5回転
・ 客単価 4,000円 月25日稼働
売上予測(1ヵ月)=4,000円×2台×4.5回転×25日=90万円
③ 労働集約的な業種(自動車販売業、化粧品販売業、ビル清掃業など)
<算式> 従業者1人当たりの売上高 × 従業者数
[設例] 業種:自動車小売業
・ 従業者 3人
・ 従業者 1人当たりの売上高(月間) 274万円
※「小企業の経営指標」による業界平均から算出)
売上予測(1ヵ月)=274万円×3人=822万円
④ 設備能力が直接売上に結びつく業種(部品製造業、印刷業、運送業など)
<算式> 設備の生産能力 × 設備数
[設例] 業種:部品(ボルト)加工業
・ 施盤 2台
・ 1台当たりの生産能力 1日(8時間稼働)当り500個
・ 加工賃@50円 月25日稼働
売上予測(1ヵ月)=50円×500個×2台×25日=125万円
納得のできる根拠にもとづいて見込みを立てる
売上げの見込みを立てる際には、これまでの経験にもとづくデータなどがある場合にはそれを利用できますが、それがない場合には、各種統計資料や同業種の平均的な売上高などを参考にします。
公的なデータの資料としては、以下のものが参考になります。
統計資料の例
| 国勢調査 | 日本全国に住んでいる人を対象に5年に一度行われる、人口、年齢、職業、世帯数などについてのデータ。 |
| 各市町村が行う人口調査 | 各市町村の単位での総人口数、男女別数、年齢別数、昼夜人口などを表したデータ。ただし、市町村ごとに調査項目が多少異なる。 |
| 全国物価統計調査 | 消費生活において重要な支出の対象となる商品の販売価格やサービス料金、これらを取り扱う店舗の業態などについて調査したデータ |
| 小売物価統計調査 | 消費生活において重要な商品の小売価格やサービスの料金を全国規模で毎月調査したデータ。 |
原価・経費について
売上原価や各種経費についても、極力、根拠のあるデータにもとづいて算定するようにします。
なお、フランチャイズなどのようにすでに原価率やおよその経費が決まっている業種については、その数字にもとづいて計算します。
主な経費の種類としては、人件費・仕入れ代・家賃・水道光熱費、支払利息などがありますが、これ以外の経費がある場合には見落とさずに記入します。
また、設備などを購入する場合には、減価償却費の計上も必要です。
減価償却費は経費の一部として差し引かれるものですが、実際には利益の一部として見られます。
たとえば、利益10万円/月、減価償却費5万円/月となっている場合には、実質的な借入金の返済原資は利益の10万円/月だけでなく、減価償却費5万円/月を足した15万円/月となります。
このことは金融機関でも理解しているため、比較的高額な設備(目安30万円以上)を購入する計画を作成する際には、減価償却費の計上を忘れないようにしてください。
利益について
通常の事業では経営が軌道にのる数ヶ月間については、売上げが少なく、利益ベースで赤字となることが一般的です。
このような場合、ムリな売上げを立てる計画を作って黒字にする方がいますが、赤字の期間が3〜4ヶ月程度であればそのままの計画でも問題ありません。
しかし、銀行に対する融資の返済はこの利益により行われるため、あまり利益のマイナスが続く場合には返済ができない計画となってしまいます。
そのため、計画の作成では、返済ができるだけのキャッシュがあるかということに注意する必要があります。
たとえば、ある月の売上げが30万円で、経費が50万円の場合には、その月については20万円の赤字となってしまいます。
しかし、自己資金や前月からの繰越金が100万円ある場合には、100万円-20万円=80万円のキャッシュの余裕があるため、仮に融資の返済額が10万円だとしても返済をすることが可能です。
けれど、赤字が続いてキャッシュが0となっているときに、また20万円の赤字を出してしまったら、融資の返済ができなくなってしまいます。
したがって、当面の赤字は問題ありませんが、キャッシュを上回る返済や支払いが生じるような計画では融資は困難となりますので、利益と同様、キャッシュの残高に注意する必要があります。
「月次収支予定表」の作り方
公庫の記入例では「事業の見通し」における収支見込を「創業当初」と「1年後」の2つだけとしていますが、これでは不足のため、月別に収支予定表を作成することをおすすめします。
月単位での計画を立てることにより、月ごとの収支がいくらになるのかということや、年度の結果についての経緯がわかるため、より精緻な計画を作ることができるとともに、金融機関からの納得を得やすくなります。
収支計画の内容については、できれば月ごとに2年分程度を作成した方がベターとなります。
また、エクセルで表を作成することにより、各計算の検算が容易になり、時間の短縮や修正が簡単にできます。
なお、記入にあたりスペースが不足する場合には、内容を別紙に記入し、計画書用紙と別紙をあわせて提出することをおすすめします。この場合、計画書のフォーマットの空白には「別紙のとおり」と記載します。
公庫では、創業計画書のフォーマットをA4一枚の用紙としてまとめていますが、別にこの用紙を必ず使わなくてはならないというわけではありませんし、記入する文字数については〇文字以内が望ましいという制約もないため、必要であれば長くなってもまったく問題ありません。
また、計画の内容をエクセルで作成し、表などを印刷して資料として提出することとも可能です。
収支計画表例
| 繰越損益 | 3,000,000 | 5,592,000 | 5,684,000 | 中略 | |
| 売 上 高 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 20,500,000 | |
| 原 価 | 300,000 | 450,000 | 540,000 | 6,150,000 | |
| 売上総利益 | 700,000 | 1,050,000 | 1,260,000 | 14,350,000 | |
| ( 変動費 ) | |||||
| 社員人件費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 2,400,000 | |
| P/A人件費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 1,800,000 | |
| 宣伝広告費 | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 750,000 | |
| 通信水道光熱費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 | |
| その他経費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 360,000 | |
| 計 | 630,000 | 480,000 | 480,000 | 5,910,000 | |
| ( 固定費 ) | |||||
| 家 賃 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 2,400,000 | |
| リース料 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 360,000 | |
| 支払利息 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 216,000 | |
| 水道光熱費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,200,000 | |
| 雑費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 360,000 | |
| 減価償却費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 | |
| 計 | 428,000 | 428,000 | 428,000 | 5,136,000 | |
| 経費合計 | 1,058,000 | 908,000 | 908,000 | 11,046,000 | |
| 利 益 | -358,000 | 142,000 | 352,000 | 3,304,000 | |
| 融資借入額 | 3,000,000 | 0 | 0 | ||
| 元本返済額 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 | |
| 返済CF | 5,592,000 | 5,684,000 | 5,986,000 |
繰越損益
創業計画をはじめて作成するときには、繰越損益の箇所には自己資金額を記入しますが、すでに事業を開始している場合には、その時点での手持ちのキャッシュ額を記入します。
なお、この箇所は前月の返済CFが繰り越されてくる箇所なので、創業2月目以降については前月の「返済CF」と同じ数字を入れます。
売上関連
〖初年度目標額 20,500千円 次年度目標額 25,000千円〗
売上げについては、類似業種の計算方法、もしくは過去の経験の見込みにもとづいて算定しますが、いずれについても根拠を示すようにします。
なお、下表のようにその根拠を示すデータを売り上げの箇所に反映させるようにすると、修正や見直しを簡単に行うことができます。
| 来客層 | 利用時間帯 | 予想客単価 | 予想回転数 | 席 数 | 営業日数 | 見込売上 |
| A | 18:00~23:00 | 3,000 | 2.0 | 30 | 25 | 4,500,000 |
| B | 23:00~ 3:00 | 3,200 | 1.5 | 25 | 3,600,000 | |
| C | 3:00~ 6:00 | 3,300 | 1.0 | 25 | 2,475,000 | |
| 月計 | 10,575,000 | |||||
原価(仕入)関連
〖原価率 30% 粗利益率 70%(過去勤務店の平均実績を参照)〗
原価は、その店の売上高に仕入原価率を掛けたものをもって算出します。
原価率は自分の見込みでも構いませんが、業種別にある程度平均的な原価率が決まっているので、あまりそれを大きく逸脱しないように注意してください。(例えば、飲食店の場合には30〜35%が標準的な原価率)
また、食べ物と飲み物のように種別が異なるものについては、それぞれの原価率についても把握しておきましょう。
家 賃
〖家賃 200,000円 うち管理費10,000円〗
家賃は、実際の契約書に書かれた金額をそのまま記入します。
もし、まだ、テナントの賃貸契約が済んでいない場合には、不動産屋からもらった資料にもとづいて賃料を記入します。
なお、管理費等がある場合には、その総額を家賃として記入し、その内訳を別記します。
代表者給与
〖代表者給与 200,000円〗
法人の場合には、自分で決めた代表者の給与額をここに入れます。
代表者の給与についてはいくらでなければならないということはありませんが、これがあまり多すぎる場合には最終的な利益が少なくなる、経営者としての姿勢を疑われるなどの問題が生じる可能性があります。
また、逆に極端に少ない場合には、経営者の生活が成り立たなくなる計画となるため、20〜25万円程度としておいた方が無難といえます。
なお、個人事業の場合には、代表者の給与は最終利益からとることとなるため、ここでは入れてありません。
社員人件費・ P/A人件費
〖社員:250,000円/月 P/A:内訳を参照〗
人件費の内訳の例
| 科 目 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
| P/A人件費 | 207,000 | 207,000 | 207,000 | 621,000 |
アルバイト、パート 計2名 時給 1,000円
通常勤務分 パートA:1,000円×6.0時間×17日 102,000円 パートB:1,000円×7.0時間×15日 105,000円
ここには今後3か月以上継続して雇用を予定している社員やパート等の人件費の額を記入しますが、社員やパートが複数いる場合は上の表のようにその内訳を明らかにします。
また、複数のパート等をシフトにより使用する場合には「シフト表」を作り、月ごとにかかる費用の根拠を明確にすると説得力が増します。
宣伝広告費
〖初月にホームページの作成代として150,000円の他、毎月50,000円/を継続的に行うチラシ代として見込む。〗
宣伝広告費については、「その内容が何なのか?」(広告掲載、自社サイトの対策費、チラシ配布等)と「いくらかかるのか?」という明細とあわせて記入するようにします。
水道光熱費、通信費
〖同業種の平均データより、100,000円/月を見込む〗
通信水道光熱費は、同業種の同規模程度の店舗を参照にしますが、これが難しいような場合には、「売上げの○%」のような比率で計算してもかまいません。
その他経費関連
〖その他雑費として、30,000円/月を見込む〗
「雑費や消耗品の購入」などにかかる経費を予想して計上します。
支払い元金・利息関連
〖元金と利息については、以下のとおりに計算した。
元金:○○○千円 利率:○% 支払回数:72回払い 元金均等払い〗
元金返済額は、借入予定額を返済予定回数で割ったものを、利息は借入れ予定額利率をかけ12で割って1ヶ月あたりの額を算出します。
簡単に返済額がシミュレーションできるサイトもあるため、これを使うと簡単に計算ができますが、その際の返済方法は「元金返済」となることに注意してください。
なお、通常、支払い元金の計算は「借入希望額 ÷ 支払回数(5年払いの場合は60回)」のように計算しますが、もし、据置き期間(元本の支払いをしなくてもよい期間)を利用する場合には、その回数分を差し引いた回数(6ケ月据置の場合には60-6=54回)で計算します。
支払利息については、日本政策金融公庫の新創業融資制度の最新の金利を参考に算定しますが、同じ制度でも何年で借りるかによって金利が変わってくることに注意してください。
参考:日本政策金融公庫の金利表
返済CF
CFは「キャッシュフロー」の略であり、支払いに充てることのできる財源を意味します。
また、前出の収支計画表におけるCFは「繰越利益+利益+減価償却費+見込融資額-元本返済額」となります。
たとえば、繰越利益50万円、その月の利益20万円、減価償却費5万円、見込融資額300万円、元本返済額4万円の場合は、50万円+20万円+5万円+300万円-4万円=371万円となり、この額が翌月に繰り越されることとなります。
減価償却費
〖減価償却費については5万円/月を見込む。金額については、以下のとおり算定した。〗
原則として30万円以上の設備や備品を購入したときには、減価償却が必要となるため、その額を算定し経費に計上します。ただし、30万円未満の設備等については、それを購入した年の損金として一括して償却しても構いません。
基本的な減価償却計算(定額法)は、以下の方法で行います。
① その償却期間が何年かを国税庁の「耐用年数一覧表」で調べる
② 取得金額をその設備ごとに定められた耐用年数で割って減価償却額を計算する
③ 収支計算表を月ごとに作成する場合は、②の金額をさらに12で割ったものを1ケ月あたりの償却額とする。
なお、設備等が複数ある場合には、以下のような表にするとわかりやすくなります。
| 品 目 | 取 得 額 | 耐用年数 | 償却額/年 | 償却額/月 |
| 看 板 | 500,000円 | 5年 | 100,000円 | 83,333円 |
| 内 装 費 | 300,0000円 | 10年 | 300,000円 | 25,000円 |
| 什器(品棚) | 1,200,000円 | 6年 | 200,000円 | 16,666円 |
| 合 計 | 600,000円 | 50,000円 |
まとめ
日本政策金融公庫の創業計画「事業の見通し」の箇所は、計画の結論ともいえる収支計画について記載するものです。
そのため、その内容については、プランが妥当であることや、実現可能性が高いことを理解してもらうための根拠がどれだけ具体的に書かれているかが大きなポイントとなります。
また、収支計画の作成にあたっては、半年や1年ごとなどでまとめたものではなく、月単位のものを2年分は作成することをおすすめします。

「いい税理士さんに出会えてよかった」と言われるために、従業員一同情熱と信念を持って業務に取り組んでおります。税金についてだけではなく「補助金」「融資」「経営」などについて不安なこと、わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。